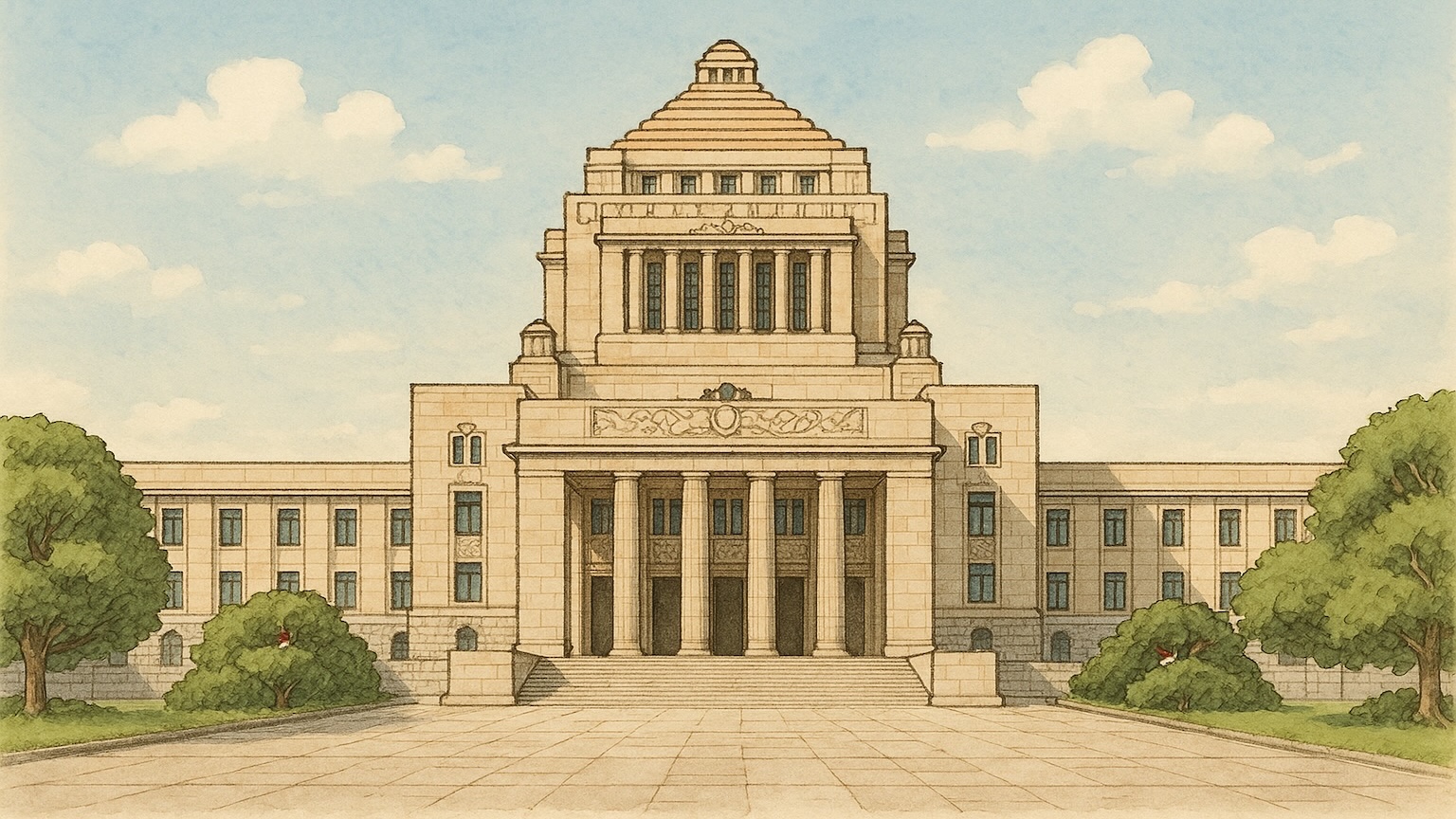参院選が公示され、各党の政策論争が活発化する中、外国人政策に関する言及が増加していることに私たちは注目せざるを得ません。人手不足を背景とした外国人労働者受け入れの拡大は、もはや避けて通れない現実であり、国内への外国人流入は今後も続くでしょう。しかし、一部で見られる「外国人が私たちの仕事を奪う」といった排外的な主張は、現実を直視せず、共生社会の実現を阻む矮小な議論であると言わざるを得ません。
「仕事を奪われる」という誤解の構造
「外国人が仕事を奪う」という言説は、多くの場合、誤解と偏見に基づいています。確かに、特定の業種や職種において、外国人労働者の増加が賃金水準に影響を与える可能性は否定できません。しかし、忘れてはならないのは、現在の日本社会が深刻な人手不足に直面しているという事実です。
例えば、建設、介護、農業といった分野では、日本人労働者だけでは需要を満たせない状況が常態化しています。このような状況下で外国人労働者は、日本人では敬遠されがちな仕事や、人手不足で滞っていた業務を補完する重要な役割を担っています。彼らがいなければ、私たちの社会生活の基盤が揺らぎかねないのです。つまり、彼らは「仕事を奪う」のではなく、むしろ「日本人だけでは回らない仕事を支えている」というのが実情です。
また、外国人労働者が増えることで、新たな需要が生まれ、経済全体が活性化する側面もあります。彼らの消費活動は地域経済に貢献し、多様な文化は新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。排外的な主張は、こうした多角的な視点を欠き、目先の不安のみに囚われていると言えるでしょう。
避けて通れない共生社会への道
一部政党が「日本人ファースト」を掲げ、外国人排斥ともとれる主張を展開する背景には、変化への不安や伝統文化の保護といった名目があるのかもしれません。しかし、世界が密接に繋がり、人の移動が活発化する現代において、特定の民族だけで社会を維持しようとする試みは非現実的です。国連の推計では、日本の人口減少は今後も続き、労働力人口の確保は喫緊の課題です。外国人なしに日本の経済社会を維持することは、もはや不可能に近いと言えます。
自民党の石破茂首相が指摘するように、「その時だけの憎しみ、悪口」では問題は決して解決しません。共産党や社民党が警鐘を鳴らすように、排外主義の台頭は、私たちが築き上げてきた自由で開かれた社会の価値を損ないかねない危険な潮流です。
建設的な議論こそが未来を拓く
私たちは、もはや「外国人が入ってくること」を前提として、いかに共生社会を築いていくかという議論に軸足を移すべきです。そのためには、感情的な排斥論ではなく、具体的な課題と向き合う建設的な議論が必要です。
例えば、外国人労働者の適正な労働条件の確保、医療や教育、住居などの生活インフラの整備、そして文化や習慣の違いから生じる摩擦を解消するための相互理解の促進などが挙げられます。クルド人問題が浮上した川口市でのヘイトスピーチは、共生社会の難しさを示す象徴的な事例ですが、こうした問題に対し、政府や自治体、そして私たち一人ひとりが具体的な解決策を模索し、実行していく責任があります。
「日本人の賃金が上がらない」という懸念に対しては、外国人労働者の受け入れを制限するのではなく、労働市場全体の構造改革や生産性向上、同一労働同一賃金の徹底といった、より本質的な議論を進めるべきです。外国人医療保険の乱用や土地取得の問題についても、感情論ではなく、制度の適正化に向けた冷静な議論が求められます。
多様な背景を持つ人々が共に生きる社会は、時に困難を伴うかもしれません。しかし、それは同時に、私たちに新たな価値観や視点をもたらし、社会全体を豊かにする可能性を秘めています。今回の参院選が、排外主義を煽る場ではなく、真の共生社会を実現するための、建設的で実りある議論が交わされる機会となることを強く望みます。