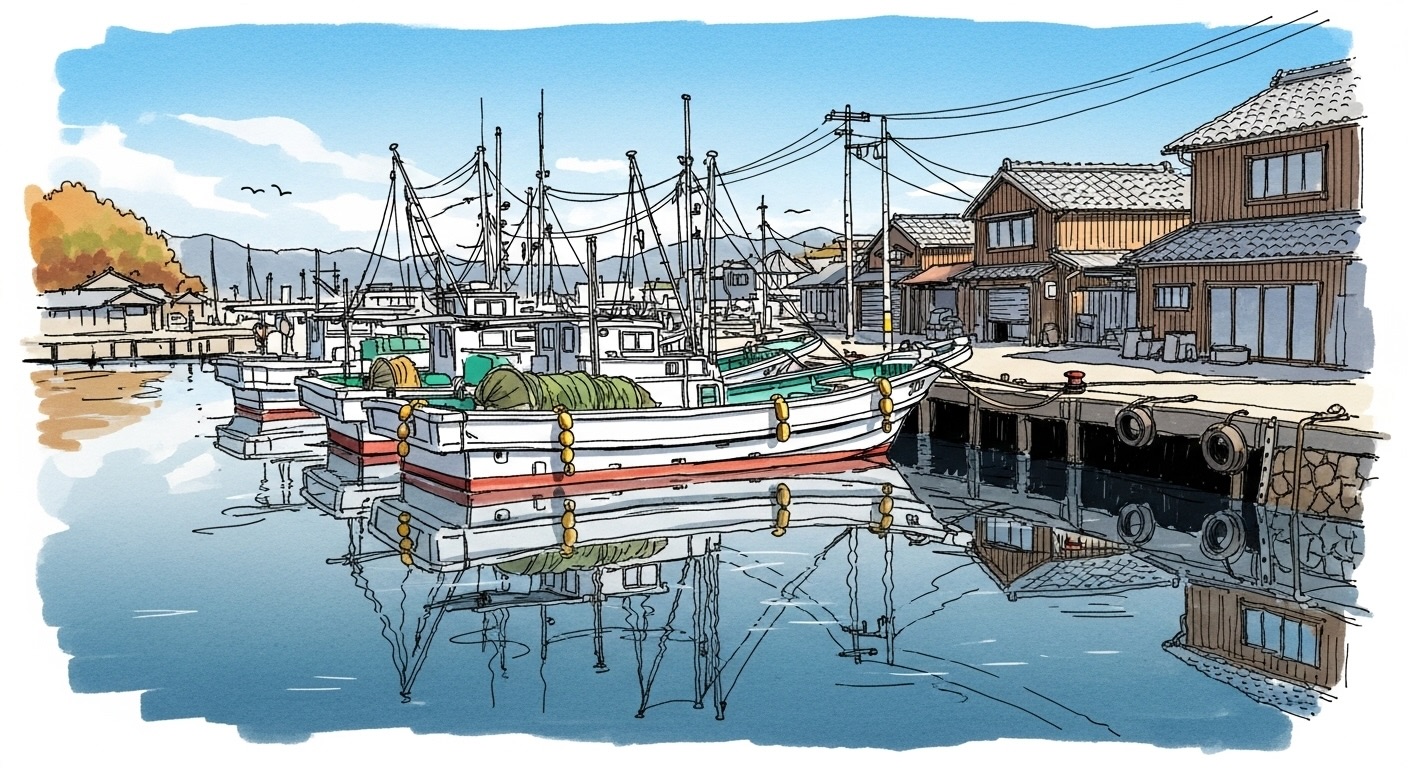日本の豊かな食卓を支えてきた漁業が、今、深刻な危機に瀕しています。人手不足、高齢化、そして労働力人口の減少。このままでは、日本の漁業そのものが維持できなくなり、私たちの食卓から新鮮な魚が消えてしまうかもしれません。
この文章では、漁業の現場で起きている「静かなる崩壊」と、それを食い止めるための唯一の希望について、統計データが突きつける衝撃的な事実とともに迫ります。
目次
崩壊の第一歩:消えゆく漁師たち
日本の漁業は、もはや「労働力」と呼べるものを失いかけています。
- 壊滅的な人員減少: 1961年に約70万人を数えた漁業就業者数は、2020年にはたったの13.5万人にまで激減しました。これは、わずか60年で5分の1以下に減少したことを意味します。この減少は、単なる労働者の減少ではなく、日本の漁業を支えてきた「知恵」や「技術」が、丸ごと失われつつあることを示しています。
- ベテラン漁師の引退ラッシュ: そして、残された漁師たちの多くは高齢者です。65歳以上が全体の約20%を占めるという現実は、今後数年の間に、彼らが一斉に現場を去っていく「引退の津波」が、漁業を襲うことを意味しています。
海の男たちは、もはや「絶滅危惧種」となりつつあるのです。
崩壊の第二歩:食卓から消える魚
漁業を担う人がいなくなれば、何が起こるか。それは、漁獲高の壊滅的な減少です。
- 漁獲高の激減: 日本の漁獲高は、ピーク時には年間約1,200万トンを誇りましたが、2020年には約300万トンにまで激減しました。これは、過去数十年間で、日本の海から4分の3の魚が消えたに等しいのです。
この減少は、乱獲だけでなく、人手不足による漁業活動の縮小が大きく影響しています。もし、このまま労働力が失われ続ければ、漁獲高はさらに半減し、私たちの食卓は、輸入された魚介類に頼るか、高価な「贅沢品」としての魚を受け入れるしかないでしょう。
最後の希望:外国人材が「海の戦力」となる日
この暗い未来を食い止める、唯一の現実的な解決策が、外国人材の力です。
1. 外国人材が働くための在留資格
日本の漁業分野で働く外国人材の主な在留資格は、即戦力人材を対象とした「特定技能」と、技術移転を目的とした「技能実習」の二つです。特に特定技能は、2019年の制度創設以降、人手不足分野における新たな労働力として期待されています。
2. 受け入れの現状と主な出身国
出入国在留管理庁のデータ(2024年6月末時点)によると、特定技能の在留資格で漁業に従事している外国人数は約2,452人です。その中でも、インドネシア人が圧倒的に多く、約80.8%を占めています。次いでベトナムやフィリピンなどが続きます。
3. 政府の受け入れ計画と達成状況
政府は、この切迫した危機を認識し、漁業分野における特定技能外国人材の受け入れ見込み数を、2024年度からの5年間で最大17,000人と設定しています。しかし、2024年6月末時点での受け入れ人数は約2,452人であり、現時点では計画を大きく下回っているのが現状です。
このままでは、日本の漁業は立ち行かなくなると判断されたため、政府は外国人材の受け入れを強力に推進しています。外国人材は、日本の漁業技術を継承し、新しい力を注入することで、日本の漁業を再生させる「最後の希望」なのです。
彼らの受け入れは、もはや待ったなしの状況であり、日本の豊かな海と、私たちの食文化を守るための未来への投資なのです。
記事の出典・参考資料