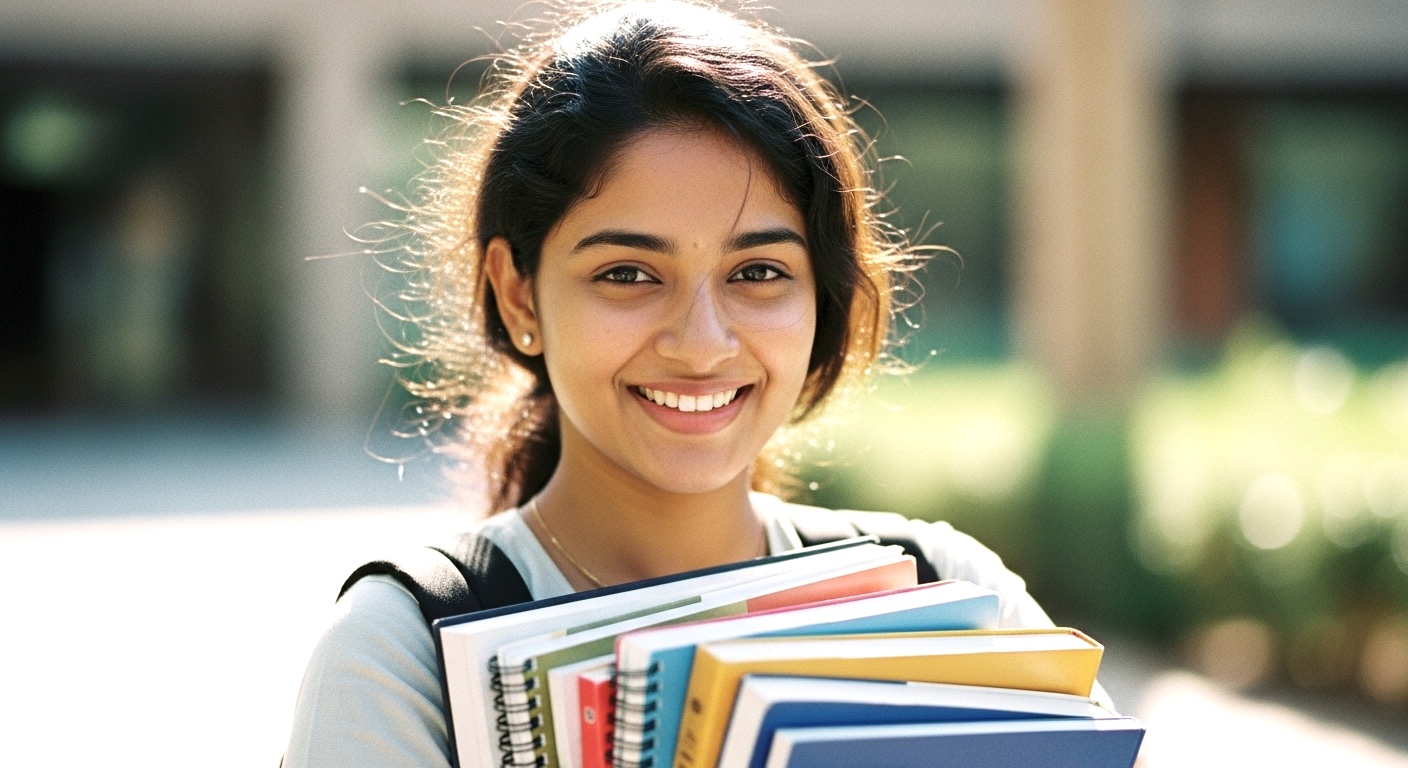人手不足が深刻化し、外国人材の受け入れが拡大する中で、現場から「来日する労働者の日本語能力が不十分だ」という批判の声が聞かれることがあります。しかし、この批判は、日本語という言語が持つ特殊性と、その習得に要する途方もない労力を理解していない、安易なものであると言わざるを得ません。
日本語は、世界の主要言語と比較しても極めて特殊な構造を持ち、ネイティブスピーカーが考える以上に、外国人にとってマスターすることが難しい言語の一つです。
目次
習得難易度を測る「三つの壁」
日本語が外国人学習者にとって世界屈指の難関とされる背景には、主に以下の三つの「壁」が存在します。
障壁①:文字体系の複雑性(世界でも稀な「三重構造」)
多くの言語はアルファベットや単一の表音文字(ハングルなど)を用いますが、日本語はひらがな(表音文字)、カタカナ(表音文字)、そして漢字(表意文字)という、3つの異なる文字体系を同時に運用します。状況に応じて用いられるローマ字も入れると4つになります。
特に漢字は、その一つ一つが意味を持ち、一つの漢字に対して複数の読み方(音読みと訓読み)があるため、習得には膨大な記憶量が必要です。米国務省傘下のFSI(Foreign Service Institute)の分類では、日本語は「学習が最も困難なカテゴリーV」に分類され、英語話者が習得するには約2200時間の学習が必要とされています。これは、フランス語やスペイン語(約600時間)の約3.6倍に相当する時間です。
障壁②:文法の特殊性と「曖昧さ」
日本語の文法は、語順が「主語―目的語―動詞(SOV型)」であり、世界の主要言語の主流である「主語―動詞―目的語(SVO型)」とは異なります。
さらに特殊なのが、文脈で主語が省略されることが日常的である点です。誰が、何を、どうしたのか、という情報を文脈や状況から推測する必要があり、論理構造が明確な欧米語話者にとっては極めて習得が困難な要素です。
障壁③:社会的な複雑性「敬語システム」
日本語の敬語システムは、単に丁寧な言葉遣いというだけでなく、話者と聞き手の社会的な地位、年齢、関係性に応じて言葉を使い分ける必要があります。
- 謙譲語: 自分を下げる
- 尊敬語: 相手を高める
- 丁寧語: 丁寧に述べる
これらを瞬時に使い分け、さらに場面に合わせて適切な語彙を選択する能力は、単なる言語能力を超えた高度な社会文化的理解を必要とします。この複雑な社会言語学的なルールは、外国人が「流暢に話せる」レベルに達した後も、常に大きな障壁として立ちはだかります。
「安易な批判」がもたらす問題
外国人労働者は、特定技能制度の入国要件として日本語能力試験N4(基本的な会話や読み書きができるレベル)をクリアするか、それ相当の日本語学習を経て来日しています。彼らは、上記のような極めて高い障壁を乗り越えようと努力している最中なのです。
ネイティブの日本人にとっては、日本語は「空気のように自然なもの」かもしれませんが、その特殊性を理解せず、「なぜもっと上達しないのか」「会話がスムーズでない」と安易に批判することは、以下の問題を引き起こします。
- モチベーションの低下: 努力を否定されたと感じ、日本語学習へのモチベーションを著しく低下させます。
- コミュニケーションの機会損失: 批判を恐れて発言を控え、結果的に職場でのコミュニケーションが滞り、安全管理上のリスクや生産性の低下につながります。
- 国際的なイメージの悪化: 日本の受け入れ側が外国人材の努力に理解を示さない姿勢は、「日本は働きづらい」という国際的な評判につながり、優秀な人材の獲得競争において日本が不利になる可能性があります。
日本が今後も労働力を維持し、国際社会との共生を進めるためには、外国人材が持つ日本語の能力を批判するのではなく、彼らが直面する言語の壁を理解し、支援し、共に働くための工夫こそが必要です。彼らの努力を称賛し、不完全な日本語でも安心して発言できる環境を作ること。それこそが、人手不足の時代に私たち日本人が持つべき「新しい共生意識」と言えるでしょう。