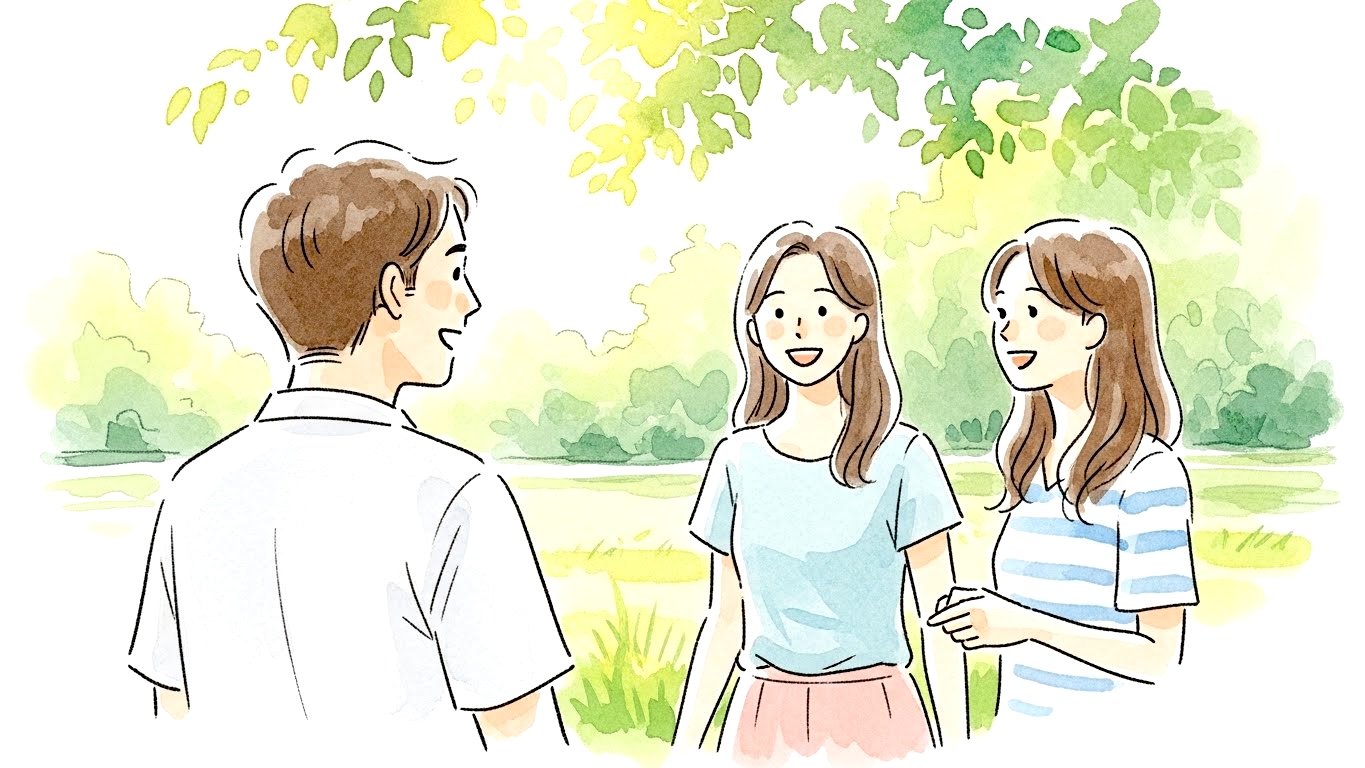街角に色鮮やかなイルミネーションが灯り、華やかな賛美歌の旋律が流れる季節となった。日本では、特定の信仰を持たずとも、クリスマスを冬の風物詩として楽しむ光景が定着して久しい。正月に神社へ参り、仏式で先祖を弔いながら、キリスト教の祝祭をも生活の一部として取り入れる。こうした日本の習俗的な寛容さは、外来の文化を柔軟に消化してきた歴史の産物とも言えるだろう。だが、この「日本的な当たり前」が、共に働く外国人社員にとって、時として逃げ場のない心理的な圧迫となり得ることに、私たちはもっと自覚的であるべきだ。
近年、特定技能ビザをはじめとする制度の拡充により、日本の労働現場を支える外国人材は急増している。彼らの出身地や文化的背景は多岐にわたり、当然ながらそこには厳格な宗教的信条を持つ人々も含まれる。日本人の多くにとって、職場でのクリスマス会や関連するイベントへの誘いは、親睦を深めようとする善意の現れかもしれない。しかし、ある種の宗教や宗派において、他宗教の祝祭に参加することは、自らのアイデンティティーや教義を脅かす深刻な問題になり得る。良かれと思って掛けた「一緒に祝おう」という言葉が、相手にとっては断りづらい同調圧力として機能し、無用な軋轢を生んでしまう危うさを孕んでいるのだ。
特に懸念されるのは、日本企業特有の「和」を重んじる風潮である。周囲が盛り上がっている中で一人だけ参加を辞退することは、組織の中での疎外感を招くのではないか。そうした不安を外国人社員に抱かせること自体、真の共生からは程遠い。信仰は個人の内面に深く根ざしたものであり、他者が安易に踏み込むべき領域ではない。たとえそれが祝祭という華やかな形をとっていたとしても、祝わない権利や、関わらない自由は厳格に守られなければならない。
外国人雇用がさらに拡大し、社会の多層化が進むこれからの時代、企業に求められるのは「自分たちの文化に馴染ませる」ことではなく、「違いを認め、共存する」ための作法を学ぶことである。それは単に宗教知識を暗記することではない。自分にとっての日常が、相手にとっての非日常や禁忌であるかもしれないという、想像力の翼を広げることだ。相手の沈黙や、誘いに対する微かな逡巡の中に、どのような文化的背景が隠れているのか。その問いを常に持ち続けることが、職場におけるコミュニケーションの出発点となるべきである。
季節の行事を通じて親睦を図ること自体を否定する必要はない。しかし、その場の設計には、多様な価値観への細やかな配慮が不可欠だ。参加を完全に任意とし、不参加が不利益にならないことを明示する。あるいは、特定の宗教色を排した「年末の労い」として別の形を模索する。そうした地道な配慮の積み重ねこそが、外国人材が安心して能力を発揮できる、真に「心理的安全性」の高い職場を築く礎となる。多様な人々が共生する社会の実現は、こうした身近な一歩から始まるはずだ。