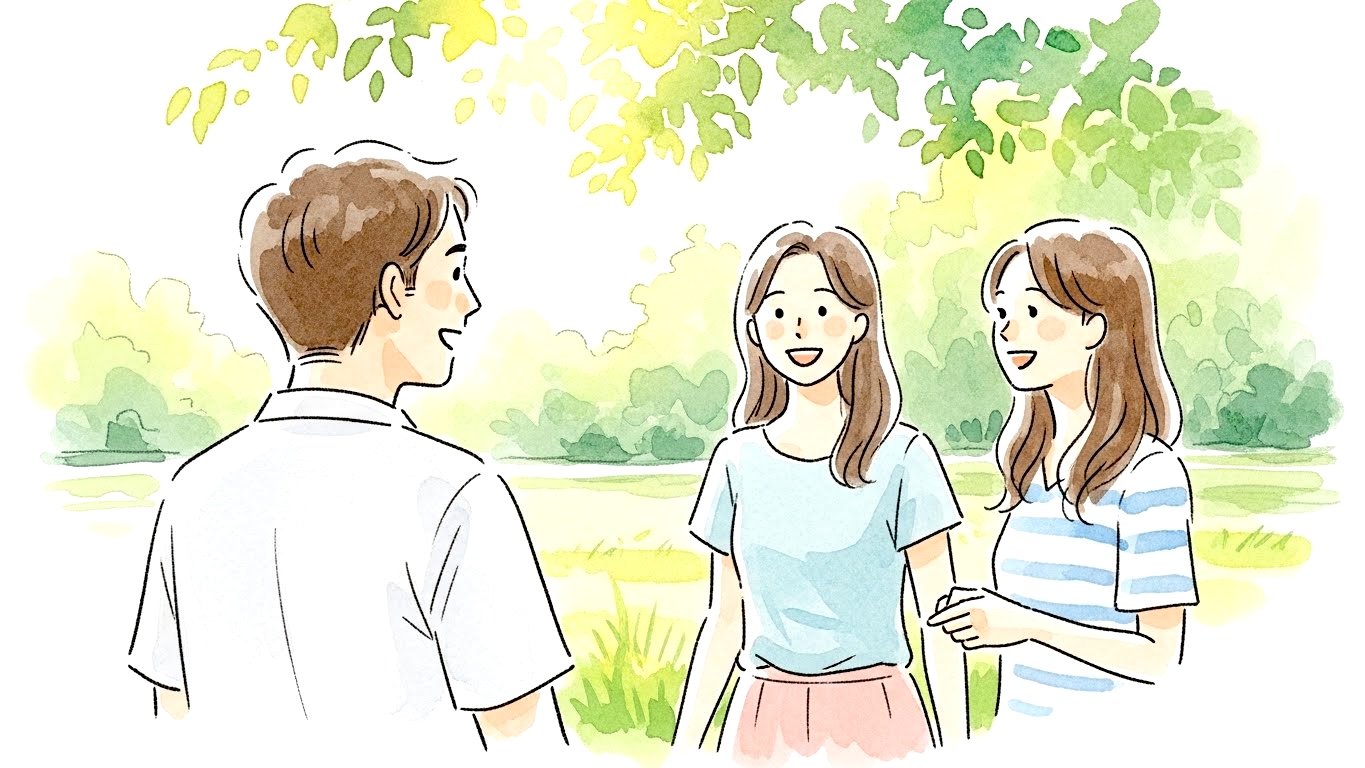2026年、日本の外国人材受け入れ制度は、積年の「建前」という重石を脱ぎ捨て、未曾有の激変期へと突入する。明2027年の「育成就労制度」本格施行に向け、本年、新たな「監理支援機関」としての許可申請が先行して開始されるからだ。これは管理団体からの単なる名称変更ではない。これまで技能実習制度という歪んだ枠組みの中で、ある種の「既得権益」を享受してきた監理団体に対し、その存在価値を問い直す峻烈な淘汰の始まりである。
「管理」から「支援」への不連続な転換
これまでの技能実習制度において、多くの監理団体は「失踪防止」という名の監視に終始し、実習生を低賃金労働力として固定化する一翼を担ってきた。そこには、送り出し機関との不透明な関係や、実習生の自由を縛ることで得られる安定的な手数料収入という甘えがあったことは否定できまい。
しかし、新制度が突きつけるのは「転籍(転職)の自由」という、市場原理に基づく当然の権利である。育成就労の目的が、国際貢献から「国内人材の確保・育成」へと転換される以上、監理団体に求められるのは、もはや物理的な「管理」ではない。人材がその企業に留まりたいと思える環境を整える「支援」の質、その一点に集約される。
特定技能への橋渡しこそが生命線
新制度の成否を分けるのは、3年間の育成就労を終えた人材を、いかに円滑に「特定技能」へと繋げられるかにある。
監理団体にとって、2026年はその「育成能力」を証明すべき年となるだろう。日本語教育の徹底はもとより、特定技能1号・2号へと続くキャリアパスを企業と共に描き、実行する。この高度なコンサルティング能力を持たぬ団体は、転籍という荒波の中で存在意義を失い、市場から退場を命じられるに違いない。
海外送り出し機関との「癒着」を断て
同時に、海外の送り出し機関との関係も、根本的な見直しを迫られている。
不当な手数料や借金を背負わせる送り出し機関との癒着は、今や企業にとって最大の人権リスクである。投資家や国際社会が厳しく監視する中、監理支援機関が選ぶべきは、現地行政と直接連携し、透明性の高い教育を行うクリーンな機関である。インドネシアの例で言えば、インドネシア地方政府と直接MOU(覚書)を締結し、公的な枠組みで人材を送り出すといった「ガバナンスの正常化」が、受け入れ企業の信頼を勝ち取る最低条件となる。
2026年、決別の年
2026年は、過去の成功体験に固執し、変化を拒む団体にとって「終わりの始まり」となるだろう。逆に、人材を「預かる対象」から「共に育てる資本」へと認識を改め、企業の人的資本経営を支える真のパートナーへと進化する団体にとっては、躍進の年となるはずだ。
既得権益の安逸に浸る時間は、もう残されていない。制度の激変を、日本の労働市場を正常化させる好機と捉えられるか。監理支援機関としての、真の覚悟が問われている。