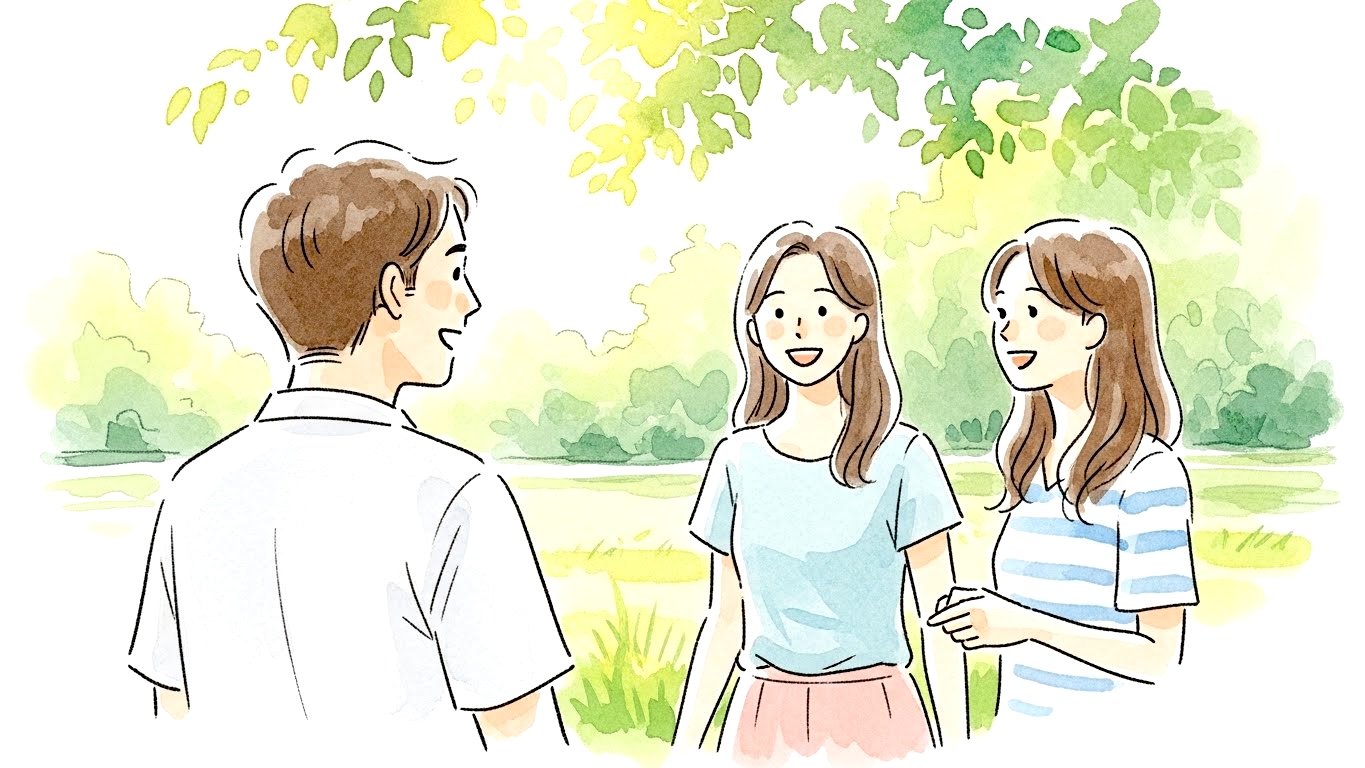日本は今、外国人労働者の受け入れを「一時的な労働力確保」から「定住を前提とした共生」へと大きく転換しつつある。特定技能2号の対象拡大は、その象徴であり、事実上、日本社会が「移民社会」へと舵を切ったと言っても過言ではない。
しかし、その一方で決定的に置き去りにされている問いがある。――彼らは日本で、いかに老い、いかにして尊厳ある老後を送るのか、という問題である。
その問いに、すでに現実が静かに、しかし重く答えを突きつけている。
群馬県のある支援施設で、一台のベッドとスーツケースに囲まれて暮らす72歳の日系ブラジル人男性ササハラ(仮名)さんの姿は、決して「過去の遺物」ではない。それは、適切な対策を講じぬまま突き進む日本の外国人雇用政策が、数十年後に直面する「未来の自画像」である。
特定技能2号の対象拡大により、わが国は事実上の「移民社会」へと舵を切ったと言える。家族を呼び寄せ、日本を終の棲家とする外国人が増えることは、労働力不足に悩む社会にとって不可欠な歩みだ。しかし、彼らが日本でいかに老い、いかにして尊厳ある余生を送るかという議論は、あまり耳にしない。
厚生労働省が公表した令和6年度のデータは衝撃的だ。外国人の国民年金納付率は49.7%。全体の84.5%という数字に比して、35ポイント近い乖離がある。この「二人に一人が無年金」という異常事態を放置したまま定住化を進めることは、将来的に膨大な社会的コストを次世代に押し付けることに他ならない。
背景にあるのは、かつての日系人労働者が陥った「出稼ぎバイアス」である。「すぐ帰るつもりだから」「仕組みが分からないから」という理由で年金加入を回避し、結果として老後に生活保護や支援施設に頼らざるを得なくなる。群馬県で取材に応じたササハラさんの「将来のことは考えていなかった」という告白は、制度の周知不足と、その場しのぎの労働力確保に終始した日本の落ち度を鋭く突いている。
これから特定技能2号を目指す若者たちに、同じ轍を踏ませてはならない。永住への道筋が拓かれた今、「年金を払うこと」は、単なる法的義務を超えた「日本で生き抜くための生存戦略」である。永住許可の審査において年金納付状況が厳格化されているのも、無年金による「老後破産」を防ぐための最低限のハードルと言える。
企業側の責任も重い。外国人を単なる「労働力」として消費する時代は終わった。社会保険完備の徹底はもちろん、多言語による年金制度の啓発、そして「脱退一時金」を安易に受け取ることのリスクを伝える姿勢が求められる。制度を知らぬまま20年、30年と働き、体が動かなくなった時に「知らなかった」と絶望させるような不作為は、共生社会の名に値しない。
外国人の高齢化の波は、確実に、そして急速に押し寄せている。日系ブラジル人の高齢者がこの10年で3倍に増えた事実は、数十年後の特定技能世代の姿そのものを映し出している。
真の共生とは、共に働き、共に支え合い、共に安心して老いることができる社会を指す。政府、企業、そして労働者本人が、今この瞬間から「老後の備え」を共通の課題として直視しなければ、日本の外国人雇用政策は、未来において「制度的困窮」という名の破綻を招くことになるだろう。