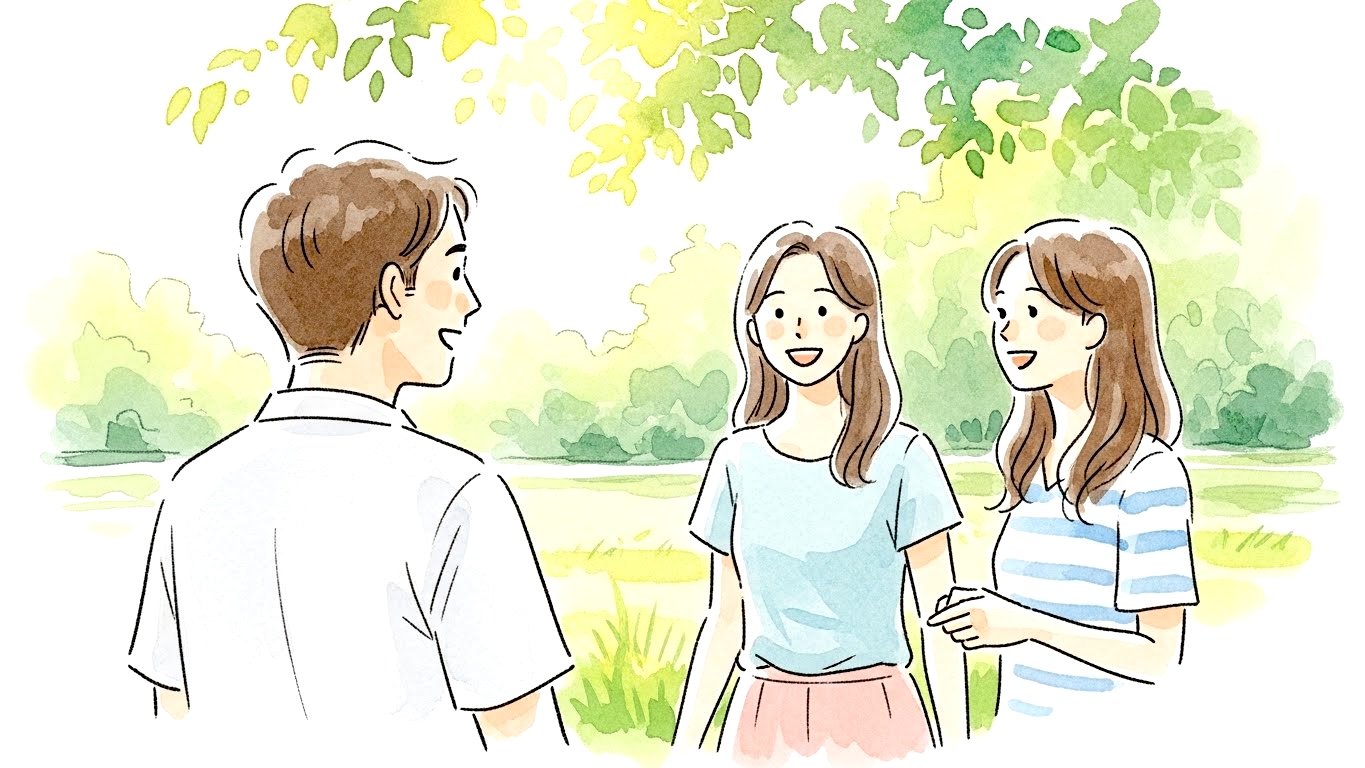2026年、日本の外国人雇用制度は大きな転換点を迎えます。2027年4月1日に「育成就労制度」が本格施行されるのを前に、今年は新制度への移行準備が本格化する年となります。特に、企業と外国人労働者をつなぐ「監理団体」のあり方が大きく変わる見通しです。
新制度に対応できない団体は、許可を得られず、事実上、事業継続が困難になる可能性もあります。受け入れ企業にとっては、提携先の選択が今後の採用計画そのものを左右します。2026年の現時点で何を確認すべきか、新制度のポイントとともに整理します。
監理団体から「監理支援機関」へ 本年から申請・認定が本格化
育成就労制度は、従来の技能実習制度に代わる新たな枠組みとして導入されます。これに伴い、これまでの「監理団体」は「監理支援機関」と名称を改め、より厳格な基準の下で許可を受ける必要が生じます。
本年中頃からは、監理支援機関としての許可申請や、育成就労計画の認定手続きが先行して始まる見込みです。審査基準は従来より大幅に厳しくなり、体制が整わない団体は申請を断念したり、不許可となるケースも想定されます。
なぜ「淘汰」が起きるのか
新制度では、「国際貢献」という理念を前面に出した従来の枠組みから、「労働力の確保と人材育成」を明確な目的とする制度へと性格が変わります。これにより、支援機関に求められる役割も大きく拡張されます。
特に重視されるのは、次のような点です。
- 転籍(転職)支援への対応体制
- 日本語教育への関与・コミットメント
- 外部監査・コンプライアンス体制の強化
これらに対応するためには、相応のコストと専門性が必要です。その負担に耐えられない団体や、従来型の管理体制から脱却できない団体は、制度移行の過程で自然にふるいにかけられていきます。
受け入れ企業が確認すべき5つの視点
育成就労外国人を雇用する「受け入れ企業」にとって重要なのは、提携する団体が新制度に対応できるかどうかを早めに見極めることです。少なくとも次の点は確認しておく必要があります。
- 育成就労制度に基づく許可申請の意思
- 転籍制度の説明能力と対応フロー
- 日本語学習支援の具体的仕組み
- 外部監査およびコンプライアンス体制
- 特定技能へのキャリア移行支援の有無と質
これらが曖昧な場合、将来的に受け入れが継続できなくなるリスクも否定できません。
企業に求められるのは「選ばれる側」への転換
監理団体が選別されるということは、同時に受け入れ企業も選ばれる立場になることを意味します。複数の支援機関との関係構築を進めるなど、調達ルートの分散を検討することも一案です。
また、転籍が制度上認められる以上、企業側には「転籍されない職場」であること、すなわち働きやすさや成長機会を提供できる職場であることが、これまで以上に重要になります。
2026年は、制度移行に向けた準備期間であると同時に、企業の姿勢そのものが問われる年でもあります。「これまで通り」が通用しなくなる中で、パートナー選びと自社の体制を見直すことが、今後の人材確保の鍵になります。