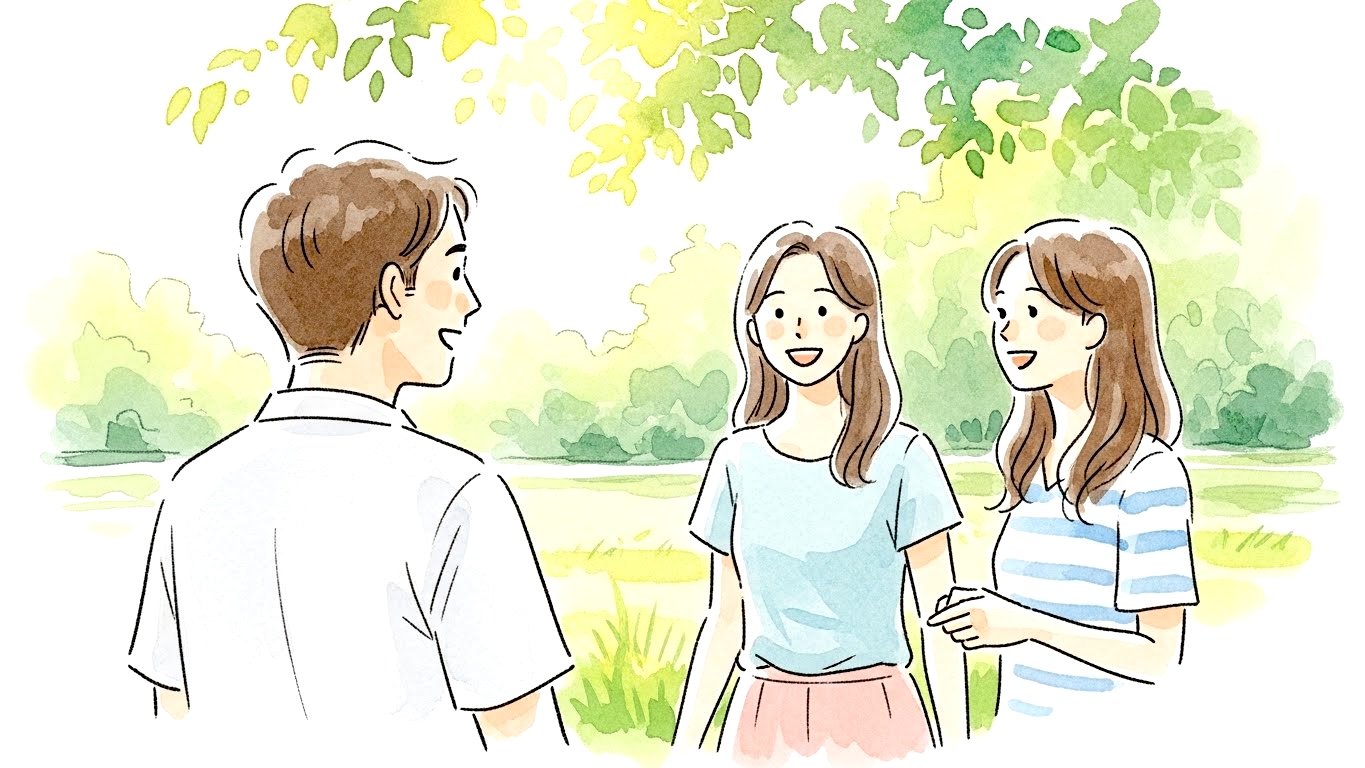日本の産業界を支える不可欠なパートナーとして、ベトナム人労働者の存在感は年々高まっている。外食業や製造業、介護の最前線など、彼らの奮闘なしに今の日本社会は立ち行かないといっても過言ではない。しかし、共に歩むべき隣人として彼らを受け入れるなかで、私たちは真に彼らの「心」に寄り添えているだろうか。その試金石とも言えるのが、ベトナム最大の伝統行事である旧正月「テト」を巡る問題である。
ベトナムの人々にとって、テトは単なる休暇ではない。一族が集い、先祖に感謝を捧げる一年で最も神聖な時間だ。日本で働く彼らの多くは、この時期を祖国で過ごしたいと切望している。職責を全うするために帰国を断念し、異郷の地で寂しさを堪える者がいる一方で、家族からの強い要望もあり、二週間から一ヶ月に及ぶ長期帰国を希望する者も少なくない。
こうした要望に対し、日本の雇用主や人事担当者が困惑するケースが相次いでいるという。人手不足が常態化するなか、一ヶ月もの不在は現場の運用に大きな穴を開けかねないからだ。だが、ここで対話を拒絶し、一律に希望を却下し続けることは得策ではない。無理な引き止めは働く意欲を削ぎ、結果として貴重な人材の離職を招くという悪循環に陥る危惧がある。
問われているのは、互いの文化を尊重しつつ、いかに実務的な落とし所を見出すかという知恵である。解決の一石として検討すべきは、雇用契約の段階からの透明性の確保だろう。長期休暇を希望する際は三ヶ月、あるいは半年前に相談することをルール化し、業務調整の猶予を確保する。場当たり的な対応ではなく、あらかじめ予見可能な仕組みを構築することが、雇用主と労働者双方の安心感につながるはずだ。
外国人労働者を受け入れるということは、単に「労働力」を雇うことではない。その背後にある歴史や文化、家族への想いを含めて、一人の人間を丸ごと受け入れることに他ならない。テトを巡る葛藤は、単なる労務管理の課題として片付けられない側面がある。彼らがどのような文化を背負い、何を大切に生きているのか。その背景を深く精査し、歩み寄る姿勢こそが、これからの多文化共生社会における日本の企業の責務といえるのではないだろうか。