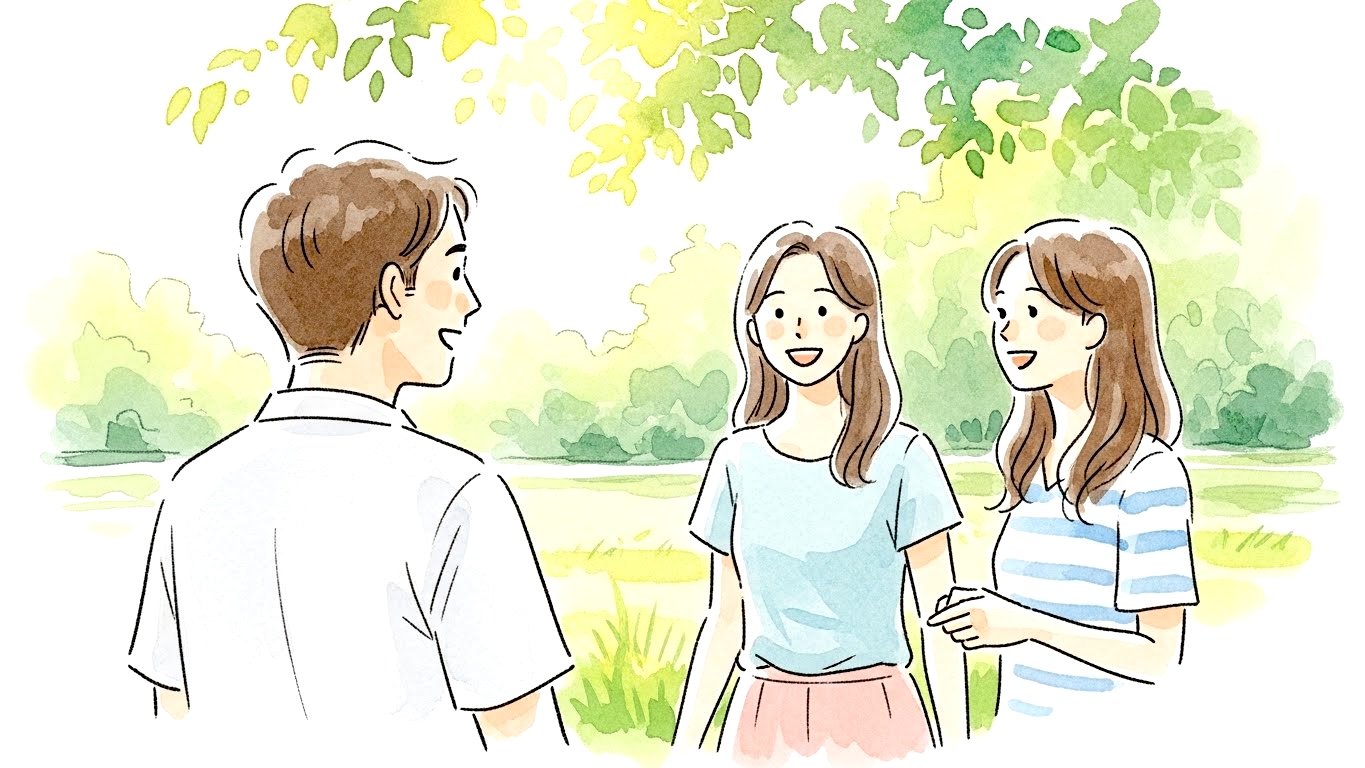外国人雇用をめぐる制度は転換点にある。技能実習制度の見直しを受け、新たに「育成就労制度」が創設され、施行日は2027年4月1日とされている。
制度が変わるということは、現場の運用も、企業の責任のあり方も変わるということだ。にもかかわらず、旧来の発想のまま「何とかなる」と構える空気が残っている。
本稿で強調したいのは、制度変更の是非を論じる以前に、企業が直面するリスクが質的に変化しているという点である。2026年は、来る制度運用を見据え、現場の弱点を点検し、手当てを進める年となる。以下、五つの論点を挙げたい。
目次
「転籍」が例外でなくなる現実
育成就労制度では、技能実習で認められてこなかった本人意向の転籍が、一定の要件の下で認められる方向が示されている。
これは、受け入れ企業にとって「人材の流動化」を意味する。転籍は「問題のある職場からの救済」だけではなく、本人のキャリア選択の一部として扱われることになる。
ここで問われるのは、賃金の多寡だけではない。教育、評価、相談体制、職場の人間関係、生活支援など、総合的に「ここで働き続ける理由」を示せるかどうかである。制度が変われば、企業は「管理する側」から「選ばれる側」へと立場が移る。その覚悟があるかが問われる。
手数料改定と“見えにくい実務コスト”
本年度より、入管への各種申請手数料が大幅に引き上げられる。これまでの数千円単位から、一部では数万円、永住申請に至っては10万円を超える増額が見込まれている。さらに、円安の定着による「手取り額」の目減りに対する補填も急務だ。外国人雇用を「安価な労働力」と捉えてきた企業にとって、このコスト増は経営を根底から揺さぶる。
ただし、手数料の多寡以上に見落とされがちなのが、実務コストである。書類作成、本人の説明、更新タイミング管理、急な不備対応、通訳・翻訳、社内調整 ― これらは表に出にくいが、確実に企業の負担となる。制度転換期には、運用が固まるまでの混乱も起きやすい。企業は、費用の増減だけではなく、手続き運用そのものを“コスト構造”として捉え直すべきだ。
監理体制の再編と「依存」の危うさ
育成就労制度の下では、技能実習の監理団体に相当する組織が「監理支援機関」へと位置づけ直され、新たに許可が必要になるとされている。
この再編は、監理側だけの問題ではない。受け入れ企業が、監理機関に業務を「丸投げ」し、自社に支援の知見や体制が蓄積されていなければ、制度変更の局面で脆さが露呈する。
企業が備えるべきは、特定のパートナーへの過度な依存を減らし、複数の相談経路を持ち、社内にも最低限の運用知識を確保することだ。制度が変わるときに傷つくのは、まず現場であり、働く本人である。そのしわ寄せを避けるのは、雇用する企業の責務である。
人権デュー・ディリジェンスの実装 “紙の対応”からの脱却
外国人雇用は、人権の観点からも国際的に注目される。経済産業省は、サプライチェーンにおける人権尊重のガイドラインを政府として決定し、企業が取り組みを進めるための資料も整備している。
つまり、「人権デュー・ディリジェンス」は理念ではなく、実務として求められ始めている(経済産業省資料)。
問題は、これが形式に流れやすいことだ。採用ルートの透明性、手数料負担の適正、相談窓口の実効性、外部監査の独立性――こうした点が伴わなければ、「やっているふり」になり、かえってリスクを増幅させる。SNS等で情報が拡散しやすい環境では、労務問題が一瞬で企業の信用を損ないうる。法令遵守と人権尊重を、書類仕事ではなく経営課題として扱えるかが、企業の持続性を左右する。
むすびに:制度の変更は現場の責任の変更
育成就労制度の施行が迫るなか、2026年は制度の“準備年”であるだけでなく、外国人雇用をめぐる企業の責任を再定義する年でもある。転籍の現実、運用コスト、監理への依存、そして人権デュー・ディリジェンス。どれも、先送りすればするほど、現場にひずみが蓄積する。
外国人雇用を「不足分を埋める手段」としてだけ捉える時代は終わりつつある。人を雇う以上、育て、守り、地域と共に支える仕組みが必要だ。制度変更は、そのことを突きつけている。企業は、変化に振り回される側にとどまるのか、それとも自ら運用を設計し直す側に立つのか。問われているのは、その姿勢である。